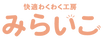アトピーと腸内環境の深い関係|リーキーガット症候群(腸もれ)編
みなさんこんにちは^^
アトピーの娘のため「着るミトンKAERA」をつくった、みらいこ代表のmidoriです。
これまでのブログで、
私たちの全身の健康のカギを握る腸について取り上げてきましたが、
アトピー性皮膚炎は、腸内環境が大きく関係していると考えられています。
今回は、
腸内環境の悪化症状の一つとして、アトピーや、全身のいろいろな体調不良引き起こす、
リーキーガット症候群(腸漏れ症候群)についてお話ししたいと思います。
リーキー ガット
Leaky(漏れる) Gut(腸)
文字通り、「腸から漏れ出る」という症状なのですが、
リーキーガット症候群がどういうものなのかを説明するにあたり、
まずは、「腸菅バリア」について知っておきましょう^^
免疫細胞の約70%が集まるといわれている腸は、
食物の消化と栄養素の吸収をする器官ですが、
消化吸収されなかった食物成分、常在細菌、病原菌などなど、
とてもたくさんの雑多な物質が通過したり、滞留しているところでもあります。
身体にとって有害なものが分別なく体内に侵入してしまっては困るので、
腸壁には、必要な栄養素を吸収しつつも、
食物アレルギー物質や、細菌毒素など、身体の中に入れてはいけないものをブロックする
という特別なバリアシステムが備わっているんです^^
1つ目のバリアは
以前のブログにも登場した腸内細菌叢(腸内フローラ)で、
約1000種類からなる細菌のメンバー構成が、多様な善玉菌が優位になっている
バランスの良い腸内環境を維持することで、病原性の高い菌を排除してくれます。
2つ目のバリアは
腸管の内側表面にびっしりと連なっている上皮細胞と、
その上を覆うように上皮細胞から分泌された粘液の層(ムチン層)によって形成されています。
ムチン層が最前線で、
外からの細菌やいろいろな物質が、直接、腸の上皮細胞に触れないよう防御してくれている下で、
ずらりと並んだ上皮細胞同士が、ガッチリとスクラムを組んで腸壁を作っています。
さらに、
腸壁に隙間ができないよう、タンパク質でできたタイトジャンクションという接着剤のような存在が、細胞間をピッタリと連結させて、体内で使われる栄養素などの小さな分子がすり抜けるための隙間は確保しつつ、有害物質の侵入を防いでいます。
3つ目のバリアは、
上皮細胞から分泌され、病原菌が増えないよう退治してくれる抗菌物質や、
免疫をコントロールする細胞たちです。
これらの腸管バリアが何らかの原因で傷ついて
上皮細胞同士の固いスクラムが緩んでしまうことで、
本来なら取り込まれることのない様々な異物が腸壁をすり抜けてしまい、
血管内や体内に漏れ出す状態を、
「リーキーガット症候群」といいます。
こうなると、通してはいけない病原菌やカビ、
他の有害物質等がどんどん体内に侵入していき、
異物の侵入に気づいた私たちの身体の免疫チームが、
連携をとって攻撃を始めることによって、
食物アレルギーや炎症、アレルギー反応(アトピー性皮膚炎・花粉症など)を引き起こす
といったように、身体のあちこちで悪さをするんですね。。
それでは、
どうして腸管バリアが緩んでしまうのでしょう?
リーキーガットの原因として良く知られているのが、
小麦タンパク質であるグルテンです。
パンやパスタ、ケーキ等、小麦製品を食べると、
タンパク質成分のグルテンが分解されてできるグリアジンが、
腸の表面を覆っている上皮細胞にくっつくことが合図になって、
ゾヌリンというたんぱく質がたくさん分泌されます。
分泌されたゾヌリンは、
上皮細胞同士を密着させているタイトジャンクションを緩めてしまう働きがあるんですね。
グルテンのほかにも、
タイトジャンクションを弱める作用のある食品成分として、
アルコール
カフェイン
カニやエビの殻などに含まれるキトサン、
唐辛子成分
などが分かっています。
この他にも、
私たちの日常生活の中に、
リーキーガット症候群を引き起こすいろいろな要因が潜んでいます。
・除菌殺菌スプレーなどを多用する過剰な清潔志向が、腸内細菌を減らしてしまいます。
・過食・偏食で胃や小腸で消化吸収しきれない食べ物が大腸で腐敗し、悪玉菌を増やします。
・慢性的なストレスや不規則な生活、運動不足、睡眠不足などで自律神経失調をきたすと、
便秘もしやすく、腸内細菌のバランスに影響を与えて腸壁に炎症を起こしやすくなります。
・食品添加物、残留農薬、遺伝子組み換え食品、水道水の塩素
などによって発生する活性酸素が、腸内細菌を減らしてしまいます。
・砂糖、人工甘味料、糖質が多く食物繊維の少ない食事は、悪玉菌が増え、善玉菌が減ります。
・防腐剤、漂白剤など殺菌成分を含む食品の摂りすぎが、腸内細菌バランスに影響します。
・抗生物質・ステロイド剤・痛み止め・ピルなど、薬の多用により善玉菌が減少します。
・カンジタ感染によって、腸管を守っているバリア機能が崩されてしまいます。
これらは全て、腸内の慢性炎症につながる原因で、
リーキーガットになる前には、腸内環境の悪化が起きているということが分かります。
ということは、
リーキーガット症候群を改善するためには、
食事を見直して腸内細菌バランスを整えること、
そして、腸の動きを悪くしてしまうストレスを発散させること、
不要な医薬品などを控えることも意識してみると良いですね^^
ここでもやはり大切なのは、
先ず、何を取り入れるかよりも、
何を入れないかということが重要になります。
ここまでで長くなってしまいましたので、
次回に、リーキーガット症候群を改善するためにできることを
もう少し詳しく書いてみたいと思います^^
みなさんの今日が、豊かで素敵な一日でありますように。
それではまた、次回のブログでお会いしましょう!
アトピーの娘のため「着るミトンKAERA」をつくった、みらいこ代表のmidoriです。
これまでのブログで、
私たちの全身の健康のカギを握る腸について取り上げてきましたが、
アトピー性皮膚炎は、腸内環境が大きく関係していると考えられています。
今回は、
腸内環境の悪化症状の一つとして、アトピーや、全身のいろいろな体調不良引き起こす、
リーキーガット症候群(腸漏れ症候群)についてお話ししたいと思います。
リーキー ガット
Leaky(漏れる) Gut(腸)
文字通り、「腸から漏れ出る」という症状なのですが、
リーキーガット症候群がどういうものなのかを説明するにあたり、
まずは、「腸菅バリア」について知っておきましょう^^
免疫細胞の約70%が集まるといわれている腸は、
食物の消化と栄養素の吸収をする器官ですが、
消化吸収されなかった食物成分、常在細菌、病原菌などなど、
とてもたくさんの雑多な物質が通過したり、滞留しているところでもあります。
身体にとって有害なものが分別なく体内に侵入してしまっては困るので、
腸壁には、必要な栄養素を吸収しつつも、
食物アレルギー物質や、細菌毒素など、身体の中に入れてはいけないものをブロックする
という特別なバリアシステムが備わっているんです^^
1つ目のバリアは
以前のブログにも登場した腸内細菌叢(腸内フローラ)で、
約1000種類からなる細菌のメンバー構成が、多様な善玉菌が優位になっている
バランスの良い腸内環境を維持することで、病原性の高い菌を排除してくれます。
2つ目のバリアは
腸管の内側表面にびっしりと連なっている上皮細胞と、
その上を覆うように上皮細胞から分泌された粘液の層(ムチン層)によって形成されています。
ムチン層が最前線で、
外からの細菌やいろいろな物質が、直接、腸の上皮細胞に触れないよう防御してくれている下で、
ずらりと並んだ上皮細胞同士が、ガッチリとスクラムを組んで腸壁を作っています。
さらに、
腸壁に隙間ができないよう、タンパク質でできたタイトジャンクションという接着剤のような存在が、細胞間をピッタリと連結させて、体内で使われる栄養素などの小さな分子がすり抜けるための隙間は確保しつつ、有害物質の侵入を防いでいます。
3つ目のバリアは、
上皮細胞から分泌され、病原菌が増えないよう退治してくれる抗菌物質や、
免疫をコントロールする細胞たちです。
これらの腸管バリアが何らかの原因で傷ついて
上皮細胞同士の固いスクラムが緩んでしまうことで、
本来なら取り込まれることのない様々な異物が腸壁をすり抜けてしまい、
血管内や体内に漏れ出す状態を、
「リーキーガット症候群」といいます。
こうなると、通してはいけない病原菌やカビ、
他の有害物質等がどんどん体内に侵入していき、
異物の侵入に気づいた私たちの身体の免疫チームが、
連携をとって攻撃を始めることによって、
食物アレルギーや炎症、アレルギー反応(アトピー性皮膚炎・花粉症など)を引き起こす
といったように、身体のあちこちで悪さをするんですね。。
それでは、
どうして腸管バリアが緩んでしまうのでしょう?
リーキーガットの原因として良く知られているのが、
小麦タンパク質であるグルテンです。
パンやパスタ、ケーキ等、小麦製品を食べると、
タンパク質成分のグルテンが分解されてできるグリアジンが、
腸の表面を覆っている上皮細胞にくっつくことが合図になって、
ゾヌリンというたんぱく質がたくさん分泌されます。
分泌されたゾヌリンは、
上皮細胞同士を密着させているタイトジャンクションを緩めてしまう働きがあるんですね。
グルテンのほかにも、
タイトジャンクションを弱める作用のある食品成分として、
アルコール
カフェイン
カニやエビの殻などに含まれるキトサン、
唐辛子成分
などが分かっています。
この他にも、
私たちの日常生活の中に、
リーキーガット症候群を引き起こすいろいろな要因が潜んでいます。
・除菌殺菌スプレーなどを多用する過剰な清潔志向が、腸内細菌を減らしてしまいます。
・過食・偏食で胃や小腸で消化吸収しきれない食べ物が大腸で腐敗し、悪玉菌を増やします。
・慢性的なストレスや不規則な生活、運動不足、睡眠不足などで自律神経失調をきたすと、
便秘もしやすく、腸内細菌のバランスに影響を与えて腸壁に炎症を起こしやすくなります。
・食品添加物、残留農薬、遺伝子組み換え食品、水道水の塩素
などによって発生する活性酸素が、腸内細菌を減らしてしまいます。
・砂糖、人工甘味料、糖質が多く食物繊維の少ない食事は、悪玉菌が増え、善玉菌が減ります。
・防腐剤、漂白剤など殺菌成分を含む食品の摂りすぎが、腸内細菌バランスに影響します。
・抗生物質・ステロイド剤・痛み止め・ピルなど、薬の多用により善玉菌が減少します。
・カンジタ感染によって、腸管を守っているバリア機能が崩されてしまいます。
これらは全て、腸内の慢性炎症につながる原因で、
リーキーガットになる前には、腸内環境の悪化が起きているということが分かります。
ということは、
リーキーガット症候群を改善するためには、
食事を見直して腸内細菌バランスを整えること、
そして、腸の動きを悪くしてしまうストレスを発散させること、
不要な医薬品などを控えることも意識してみると良いですね^^
ここでもやはり大切なのは、
先ず、何を取り入れるかよりも、
何を入れないかということが重要になります。
ここまでで長くなってしまいましたので、
次回に、リーキーガット症候群を改善するためにできることを
もう少し詳しく書いてみたいと思います^^
みなさんの今日が、豊かで素敵な一日でありますように。
それではまた、次回のブログでお会いしましょう!