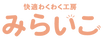リーキーガットとカンジダ菌の親密な関係
みなさんこんにちは^^
アトピーの娘のため「着るミトンKAERA」をつくった、みらいこ代表のmidoriです。
前回は、リーキーガットを引き起こす原因の一つに、
未消化の食べ物、主に未消化のタンパク質が、腸の粘膜に炎症を起こして
傷付けてしまうことがある。ということをお話しました。
リーキーガットで悩んでいる方は、
何らかの原因によって食物を分解する消化酵素が不足していて、
消化吸収力が弱くなっている場合が多いことが分かっており、
調理法や食べ方のコツで、
消化に余計なストレスがかからないようにしながら、
しっかりとタンパク質の吸収ができるようになってくると、
タンパク質をもとに作られている消化酵素の分泌も増え始め、
傷ついた細胞の修復がスムーズになってくる
という、回復への良いスパイラルになってくるんでしたね^^
さて、
今日は、
リーキーガットと深い関係にある、カンジダ菌についてお話したいと思います^^
カンジダ菌は通常、誰の体にも生息している真菌(カビ)で、
普段は日和見菌として静かに存在しているんですね。
それが、
乳化剤や防腐剤、ph調整剤などさまざまな食品添加物、
お砂糖や人工甘味料の摂り過ぎ
ジャンクフードや、それに含まれる酸化した油
過度なカフェイン、アルコール
過食などによる消化不良
抗生物質やステロイド、ピルなどの医薬品
過度のストレス
栄養不足
などなど、
腸内フローラを乱してしまい、
悪玉菌が増えることで腸内環境が悪化してくると、
おとなしかったカンジダ菌が悪玉菌チームに加勢してどんどん増殖をはじめ、
善玉菌の勢力を弱めにかかってきます。。
というのも、
悪玉菌と真菌は一緒に増殖するという特性があるからなんです。
そして、増殖したカンジダ菌は「真菌(カビ)」ですから、
腸の壁を作っている上皮細胞の表面をバリアするように覆うムチンの膜、
そして、その下の腸粘膜にまで、根深く菌糸張ることで穴を開けさせて、
リーキーガットを引き起こしてしまいます。
さらに、
悪玉菌も、悪玉菌と一緒に増殖するカンジダ菌も、
ムチンをエサにしてしまうので、腸粘膜のバリア機能を破壊してしまいます。。
結果として、
本来は体内に入ることのない、
ウイルスや菌・タンパク質といったいろいろな異物が血液中に漏れ出てしまうと、
異物を感知した免疫細胞が排除しにかけつけて、戦うことで炎症が起こります。
戦いの中で、
免疫細胞からの攻撃をかわすことに成功する細菌や異物も出てきて、
身体のあちこちで炎症を引き起こし、
例えば、
炎症が皮膚で起こるのが、アトピー性皮膚炎、
脳で起こると、うつや認知症、子どもの発達障害の症状が現れることが分かっています。
また、
カンジタ菌が増殖している事による症状として、
・甘いものを日常的に欲する
・低血糖症状が起きる(食後の眠気・記憶力、集中力の低下など)
・常に疲れていて、エネルギーがない
といったことがあります。
(カンジタ菌の増殖は検査で調べられるので、腸内環境の悪化が見られる場合は受診されてみてくださいね^^)
カンジダ菌が
リーキーガットの原因になっている場合には、
カンジダ菌を殺菌することと同時に、
減ってしまった善玉菌の数を増やし、多様性を持たせることで、
傷ついた腸の粘膜、ムチンの膜を修復させて、
腸のバリア機能を回復させながら、
根底にある腸内フローラの乱れを整えていくことが大切です^^
悪性菌やカンジダ菌が増殖するスキを与えないような
腸内フローラを育てていきましょうね♪
このムチンの存在にも、
善玉菌を増やすためにも、
食物繊維、特に水溶性食物繊維が不可欠になってきます。
それでは具体的に、
カンジダを改善する4つの方法について見てみましょう^^
1. 食事と生活習慣
・カンジタ菌のエサになるような糖質を避ける。
糖質がカンジダに良くないとされていますが、
それは、
ある意味正解で、
ある意味不正解です。
避けるべきは、
・砂糖
・健康に良いというイメージのあるハチミツでも、シロップが添加されていたり、
加熱殺菌処理されてミネラルやビタミン、酵素が排除されて、ただの糖の塊となったもの。
・ケーキやドーナッツ、菓子パン
・糖度の高い果物
といった糖質のことであり、
このような糖質は、悪玉菌の大好物で、
カンジダ菌も一緒に増殖させてしまいます。
一方で、
野菜に含まれる糖質や、
ご飯や、さつまいもの糖質については、
加熱後に冷やすことで、
糖質でありながらも食物繊維と同じ働きをするレジスタントスターチが増加することや、
以前のブログでお伝えした
善玉菌たちが腸内で「短鎖脂肪酸」を作り出すのに欠かせない「水溶性食物繊維」が
豊富に含まれていたり、体の機能を正常に維持するビタミンやミネラルを含んでいるので、
制限することで逆効果になってしまいます。
短鎖脂肪酸は、
腸内を弱酸性に保って悪玉菌の働きを抑制したり
大腸のぜん動運動を活発にしてお通じを良くしたり
腸管の粘液の分泌を促して腸のバリア機能を高めたり
殺菌・抗炎症作用があったりと、
腸内環境はもちろんのこと、
全身の健康に深く関係している腸の大事なエネルギー源なんでしたね^^
健康やダイエットのために糖質制限という言葉を良く耳にするようになりましたが、
身体に必要な糖質までも制限してしまうと本末転倒です。
ちなみに、水溶性食物繊維にはこんな食材があります♪
穀類:押し麦
野菜:ごぼう、モロヘイヤ、おくら、玉ねぎ、にんにく、らっきょう、菊芋、山芋、こんにゃく
海藻:わかめ、あおさ、海苔、ひじき、もずく、めかぶ、とろろ昆布、寒天
(※海藻の過剰摂取には気をつけましょう。)
果物/ナッツ:プルーン、アボカド、りんご、キウイフルーツ・アーモンド
誤ったダイエットで、
食べ物に対する恐怖心を植え付けてしまわないよう、
「糖質選択」をしていきましょうね^^
・ストレスケア
ストレスは私たちの身体の免疫機能に影響を与えることが分かっていて、
免疫機能は細菌と真菌の増殖をコントロールしているので、ストレスによる緊張状態を
意識的に緩めるような、入浴やストレッチ、深呼吸、ヨガなどを取り入れてみることもおすすめです。
・運動習慣
運動といっても、長時間の負荷の強い運動は全く必要ありません^^(好きな場合はok♪)
10分程度のエクササイズによって、
健康状態を整えてくれる善玉菌が増えることがわかっていて、
腸内フローラにカンジタ菌が増殖する隙間を作らないことにつながります^^
2. プロバイオティクス
プロバイオティクスは、カンジダ菌などの真菌(カビ)の増殖を抑えて、
抗真菌薬のフルコナゾールと同等の効果があることがわかっています。
また、
抗菌作用だけでなく、抗炎症作用、
腸内フローラのバランス異常を整える
といったように、
腸のさまざまな側面をポジティブに調整して
リーキーガットを改善する効果があります。
カンジダ菌の増殖によって、
善玉菌の数や多様性も少なくなってきます。
多様性とは、1つの細菌だけが突出して多くても良くないということなんですね^^
善玉菌を増やして、悪性細菌やカンジダが増殖するスキを与えないようにするために、
自分の身体に合ったプロバイオティクスは簡単に取り入れやすい方法です。
そして、腸内細菌が増えるためのエサになるプレバイオティクスも大事です♪
3. 天然抗菌ハーブ・スパイス・オイル
ある研究で、ニンニクを食事に取り入れたグループは
抗真菌薬のフルコナゾールを飲んだグループと同等の効果を得たことが分かっています。
ただし、
ニンニクを摂りすぎると、悪玉菌だけでなく、善玉菌にも影響してしまうことが分かっているので、加熱した場合の目安は1日4片、20g程度。お子様は2片程度までに抑えておくと安心です^^
その他には、
オレガノ、シナモン、クローブ、黒胡桃、ペパーミント、
よもぎ、梅干し、生姜、アップルサイダービネガーなどが、
カンジダ菌の勢いを抑えると分かっています。
また、
バジルオイル、ココナッツオイルには、カンジタ菌に対する殺菌効果があると分かっています。
4. エレメンタルダイエット(elemental diet) ー 成分栄養食で休息と回復を狙う
最後に、日本ではまだまだ聞き慣れないですが、
海外では多くの医療機関で取り入れられエビデンスが蓄積されている方法です。
私たちが必要とする栄養素をできるだけ細かい分子に加工した、
低アレルギー性の成分の流動食を摂取する治療方法で、
腸に炎症を起こしている場合、
全長約6メートルある小腸の、
最初の60~90cm位の部分で必要な栄養を吸収させてしまうことで、
腸内細菌の餌になりにくいことに加えて、残りの5mの腸の働きを休めてあげることによって、
回復を早めることにつながるというものです。
これによって、
カンジダ菌などの真菌を減らす
炎症を減らす
SIBO(小腸内細菌異常増殖)を改善する
といった効果が見られることが分かっています。
今日は、
カンジダ菌とリーキーガットの深い関係をお伝えしてきましたが、
実は、私もかつてカンジダ菌による症状に悩んでいた時期が長くあり、
ある時を境にパッタリと症状がなくなったのですが、
私の場合きっかけは、お砂糖をやめた事でした。
6年ほど前になりますが、
慢性的な疲労感と、膣の痒み、病院の検査で体内の炎症数値が高いことがわかり、
体型も気になり出していたので、お砂糖をやめたんですね^^
そうすると、あんなに好きだったスイーツに次第に興味がなくなり、
食事が楽しくなり、栄養を意識するようになりました。
栄養が満たされて、腸内環境や体調が改善してくると同時に、
脳の報酬系を揺さぶるような市販のお菓子やジャンクフードなどに
全く目が向かなくなりました。
そして、気がつけば、特に膣の痒みなどの辛い自覚症状が、
全く無くなっていたというのが私の経験です。
やはりお砂糖は良くないのと、
腸と脳、全身の健康に影響する栄養を適切に摂ることが、
とても大切だなということを身を持って実感したのでした^^
そして、今はごくごくたまーに、誕生日や何かのイベントくらいでしょうか、
スイーツを食べようかなという時があると、
原材料にこだわって作られた、美味しいスイーツを楽しむようにしています^^
そんな時は、心も身体も、みんなで幸せを感じられる最高の時間になります♪
長くなってしまいましたが、ここまでお読みいただきありがとうございました^^
みなさんの今日が、豊かで素敵な一日でありますように。
それではまた、次回のブログでお会いしましょう!
アトピーの娘のため「着るミトンKAERA」をつくった、みらいこ代表のmidoriです。
前回は、リーキーガットを引き起こす原因の一つに、
未消化の食べ物、主に未消化のタンパク質が、腸の粘膜に炎症を起こして
傷付けてしまうことがある。ということをお話しました。
リーキーガットで悩んでいる方は、
何らかの原因によって食物を分解する消化酵素が不足していて、
消化吸収力が弱くなっている場合が多いことが分かっており、
調理法や食べ方のコツで、
消化に余計なストレスがかからないようにしながら、
しっかりとタンパク質の吸収ができるようになってくると、
タンパク質をもとに作られている消化酵素の分泌も増え始め、
傷ついた細胞の修復がスムーズになってくる
という、回復への良いスパイラルになってくるんでしたね^^
さて、
今日は、
リーキーガットと深い関係にある、カンジダ菌についてお話したいと思います^^
カンジダ菌は通常、誰の体にも生息している真菌(カビ)で、
普段は日和見菌として静かに存在しているんですね。
それが、
乳化剤や防腐剤、ph調整剤などさまざまな食品添加物、
お砂糖や人工甘味料の摂り過ぎ
ジャンクフードや、それに含まれる酸化した油
過度なカフェイン、アルコール
過食などによる消化不良
抗生物質やステロイド、ピルなどの医薬品
過度のストレス
栄養不足
などなど、
腸内フローラを乱してしまい、
悪玉菌が増えることで腸内環境が悪化してくると、
おとなしかったカンジダ菌が悪玉菌チームに加勢してどんどん増殖をはじめ、
善玉菌の勢力を弱めにかかってきます。。
というのも、
悪玉菌と真菌は一緒に増殖するという特性があるからなんです。
そして、増殖したカンジダ菌は「真菌(カビ)」ですから、
腸の壁を作っている上皮細胞の表面をバリアするように覆うムチンの膜、
そして、その下の腸粘膜にまで、根深く菌糸張ることで穴を開けさせて、
リーキーガットを引き起こしてしまいます。
さらに、
悪玉菌も、悪玉菌と一緒に増殖するカンジダ菌も、
ムチンをエサにしてしまうので、腸粘膜のバリア機能を破壊してしまいます。。
結果として、
本来は体内に入ることのない、
ウイルスや菌・タンパク質といったいろいろな異物が血液中に漏れ出てしまうと、
異物を感知した免疫細胞が排除しにかけつけて、戦うことで炎症が起こります。
戦いの中で、
免疫細胞からの攻撃をかわすことに成功する細菌や異物も出てきて、
身体のあちこちで炎症を引き起こし、
例えば、
炎症が皮膚で起こるのが、アトピー性皮膚炎、
脳で起こると、うつや認知症、子どもの発達障害の症状が現れることが分かっています。
また、
カンジタ菌が増殖している事による症状として、
・甘いものを日常的に欲する
・低血糖症状が起きる(食後の眠気・記憶力、集中力の低下など)
・常に疲れていて、エネルギーがない
といったことがあります。
(カンジタ菌の増殖は検査で調べられるので、腸内環境の悪化が見られる場合は受診されてみてくださいね^^)
カンジダ菌が
リーキーガットの原因になっている場合には、
カンジダ菌を殺菌することと同時に、
減ってしまった善玉菌の数を増やし、多様性を持たせることで、
傷ついた腸の粘膜、ムチンの膜を修復させて、
腸のバリア機能を回復させながら、
根底にある腸内フローラの乱れを整えていくことが大切です^^
悪性菌やカンジダ菌が増殖するスキを与えないような
腸内フローラを育てていきましょうね♪
このムチンの存在にも、
善玉菌を増やすためにも、
食物繊維、特に水溶性食物繊維が不可欠になってきます。
それでは具体的に、
カンジダを改善する4つの方法について見てみましょう^^
1. 食事と生活習慣
・カンジタ菌のエサになるような糖質を避ける。
糖質がカンジダに良くないとされていますが、
それは、
ある意味正解で、
ある意味不正解です。
避けるべきは、
・砂糖
・健康に良いというイメージのあるハチミツでも、シロップが添加されていたり、
加熱殺菌処理されてミネラルやビタミン、酵素が排除されて、ただの糖の塊となったもの。
・ケーキやドーナッツ、菓子パン
・糖度の高い果物
といった糖質のことであり、
このような糖質は、悪玉菌の大好物で、
カンジダ菌も一緒に増殖させてしまいます。
一方で、
野菜に含まれる糖質や、
ご飯や、さつまいもの糖質については、
加熱後に冷やすことで、
糖質でありながらも食物繊維と同じ働きをするレジスタントスターチが増加することや、
以前のブログでお伝えした
善玉菌たちが腸内で「短鎖脂肪酸」を作り出すのに欠かせない「水溶性食物繊維」が
豊富に含まれていたり、体の機能を正常に維持するビタミンやミネラルを含んでいるので、
制限することで逆効果になってしまいます。
短鎖脂肪酸は、
腸内を弱酸性に保って悪玉菌の働きを抑制したり
大腸のぜん動運動を活発にしてお通じを良くしたり
腸管の粘液の分泌を促して腸のバリア機能を高めたり
殺菌・抗炎症作用があったりと、
腸内環境はもちろんのこと、
全身の健康に深く関係している腸の大事なエネルギー源なんでしたね^^
健康やダイエットのために糖質制限という言葉を良く耳にするようになりましたが、
身体に必要な糖質までも制限してしまうと本末転倒です。
ちなみに、水溶性食物繊維にはこんな食材があります♪
穀類:押し麦
野菜:ごぼう、モロヘイヤ、おくら、玉ねぎ、にんにく、らっきょう、菊芋、山芋、こんにゃく
海藻:わかめ、あおさ、海苔、ひじき、もずく、めかぶ、とろろ昆布、寒天
(※海藻の過剰摂取には気をつけましょう。)
果物/ナッツ:プルーン、アボカド、りんご、キウイフルーツ・アーモンド
誤ったダイエットで、
食べ物に対する恐怖心を植え付けてしまわないよう、
「糖質選択」をしていきましょうね^^
・ストレスケア
ストレスは私たちの身体の免疫機能に影響を与えることが分かっていて、
免疫機能は細菌と真菌の増殖をコントロールしているので、ストレスによる緊張状態を
意識的に緩めるような、入浴やストレッチ、深呼吸、ヨガなどを取り入れてみることもおすすめです。
・運動習慣
運動といっても、長時間の負荷の強い運動は全く必要ありません^^(好きな場合はok♪)
10分程度のエクササイズによって、
健康状態を整えてくれる善玉菌が増えることがわかっていて、
腸内フローラにカンジタ菌が増殖する隙間を作らないことにつながります^^
2. プロバイオティクス
プロバイオティクスは、カンジダ菌などの真菌(カビ)の増殖を抑えて、
抗真菌薬のフルコナゾールと同等の効果があることがわかっています。
また、
抗菌作用だけでなく、抗炎症作用、
腸内フローラのバランス異常を整える
といったように、
腸のさまざまな側面をポジティブに調整して
リーキーガットを改善する効果があります。
カンジダ菌の増殖によって、
善玉菌の数や多様性も少なくなってきます。
多様性とは、1つの細菌だけが突出して多くても良くないということなんですね^^
善玉菌を増やして、悪性細菌やカンジダが増殖するスキを与えないようにするために、
自分の身体に合ったプロバイオティクスは簡単に取り入れやすい方法です。
そして、腸内細菌が増えるためのエサになるプレバイオティクスも大事です♪
3. 天然抗菌ハーブ・スパイス・オイル
ある研究で、ニンニクを食事に取り入れたグループは
抗真菌薬のフルコナゾールを飲んだグループと同等の効果を得たことが分かっています。
ただし、
ニンニクを摂りすぎると、悪玉菌だけでなく、善玉菌にも影響してしまうことが分かっているので、加熱した場合の目安は1日4片、20g程度。お子様は2片程度までに抑えておくと安心です^^
その他には、
オレガノ、シナモン、クローブ、黒胡桃、ペパーミント、
よもぎ、梅干し、生姜、アップルサイダービネガーなどが、
カンジダ菌の勢いを抑えると分かっています。
また、
バジルオイル、ココナッツオイルには、カンジタ菌に対する殺菌効果があると分かっています。
4. エレメンタルダイエット(elemental diet) ー 成分栄養食で休息と回復を狙う
最後に、日本ではまだまだ聞き慣れないですが、
海外では多くの医療機関で取り入れられエビデンスが蓄積されている方法です。
私たちが必要とする栄養素をできるだけ細かい分子に加工した、
低アレルギー性の成分の流動食を摂取する治療方法で、
腸に炎症を起こしている場合、
全長約6メートルある小腸の、
最初の60~90cm位の部分で必要な栄養を吸収させてしまうことで、
腸内細菌の餌になりにくいことに加えて、残りの5mの腸の働きを休めてあげることによって、
回復を早めることにつながるというものです。
これによって、
カンジダ菌などの真菌を減らす
炎症を減らす
SIBO(小腸内細菌異常増殖)を改善する
といった効果が見られることが分かっています。
今日は、
カンジダ菌とリーキーガットの深い関係をお伝えしてきましたが、
実は、私もかつてカンジダ菌による症状に悩んでいた時期が長くあり、
ある時を境にパッタリと症状がなくなったのですが、
私の場合きっかけは、お砂糖をやめた事でした。
6年ほど前になりますが、
慢性的な疲労感と、膣の痒み、病院の検査で体内の炎症数値が高いことがわかり、
体型も気になり出していたので、お砂糖をやめたんですね^^
そうすると、あんなに好きだったスイーツに次第に興味がなくなり、
食事が楽しくなり、栄養を意識するようになりました。
栄養が満たされて、腸内環境や体調が改善してくると同時に、
脳の報酬系を揺さぶるような市販のお菓子やジャンクフードなどに
全く目が向かなくなりました。
そして、気がつけば、特に膣の痒みなどの辛い自覚症状が、
全く無くなっていたというのが私の経験です。
やはりお砂糖は良くないのと、
腸と脳、全身の健康に影響する栄養を適切に摂ることが、
とても大切だなということを身を持って実感したのでした^^
そして、今はごくごくたまーに、誕生日や何かのイベントくらいでしょうか、
スイーツを食べようかなという時があると、
原材料にこだわって作られた、美味しいスイーツを楽しむようにしています^^
そんな時は、心も身体も、みんなで幸せを感じられる最高の時間になります♪
長くなってしまいましたが、ここまでお読みいただきありがとうございました^^
みなさんの今日が、豊かで素敵な一日でありますように。
それではまた、次回のブログでお会いしましょう!