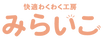絶対に知っておくべき!ジャンクフードが無性に食べたくなる理由
こんにちは!
みらいこ代表のmidoriです。
今回は、
絶対に知っておくべき!ジャンクフードが無性に食べたくなる理由
ということで、強めのテーマですが、
私たちが普段、なんとなく、腸内環境やお肌に良くないとは感じつつ、
ついつい食べ続けてしまう魅惑のジャンクフードやファストフード、
レンチンだけで、調理せずに手軽に食べられる超加工食品、
チョコレートやケーキといったスイーツや菓子パン、
どうして美味しいと感じるのでしょうか?
どうして食べ続けてしまうのでしょうか?
その仕組みにとっても関係のある、
「食と心の状態」を、前回に引き続き、一緒に紐解いていきましょう^^
そして、
満足感や快感を感じると脳内に分泌する
ドーパミンやセロトニンを上手に働かせられるようになって、
「少しずつ」の良い選択に、
「勢い」がつき、
「いつの間にか習慣化」
こうなるとあなたの完全勝利です^^
食生活を健康的にコントロールできるようになると、
たまに寄り道しても、
そんな時は余裕で楽しんで♪
新しい習慣が、ちゃんと呼び戻して整えてくれますから安心してくださいね^^
さて、
「食と心の状態」をお話しする上で欠かせないのが、
私たちの「腸」の状態なんです
え!お腹の状態と、心の状態にどんな関係があるの??
と思いますよね^^
実は、
腸は、第二の脳と言われているくらい、私たちの感情に影響しているんです。
第二の脳?腸で何か考えるの??
と不思議になってきたでしょうか^^
脳と腸が連絡を取り合うために、間に入ってメッセンジャー的な役割をしてくれる
自律神経や、ホルモン、サイトカインといった伝達物質たちが働いてくれていて、
お互いに情報のやり取りをし、密接に影響を及ぼし合っているのですが、
研究によると、
脳が、 恐怖や苦痛、不安などの強いストレスを感じたとき、その情報が腸に伝わって、
消化吸収や、下痢や便秘といった腸の機能に影響が出る、
「脳→腸」
逆に、
腸で炎症が起きたり、腸内環境のいろいろな変化が脳に伝えられて、
脳での不安感が増し、行動や食欲に変化が起きる、
「腸→脳」
というように、
「脳⇄腸」相互に影響しあう作用があることが、わかってきています。
確かに、便秘が解消してお腹の調子が良くなると、
気分まで軽やかで、爽快になることがありますよね^^
こんなことから、
腸は「第二の脳」とも呼ばれていて、
「腸の状態が、あなたの心や嗜好に影響している」
ということにも納得がいくかもしれません^^
私たちの腸には、
腸内細菌という微生物が住んでいて、
なんと、一般的な成人の腸内細菌は約1000種類あり、
数にして100兆個、総重量にして1~2 kgと言われているように、
途方もない数の腸内細菌が、集団で生息しているんですね。
その様子を、お花畑や草むらに例えて「腸内フローラ」や「腸内細菌叢(そう)」と呼ばれているんです。
お花畑や、草むらと聞くと、
なんだか腸内一面に、ワ〜っと広がっている様子がイメージしやすいのではないでしょうか^^
腸内フローラは、
私たち一人一人、そのバランスが違っていて、
毎日の食べ物や飲み物、
薬などに含まれる抗生物質、
食品添加物中の化学物質や抗菌剤などの抗菌作用、
生活スタイル
によって、
あなたが生まれてから死ぬまでの間に、さまざまな変化が起こるんですね^^
そして、
私たちが、甘いものやジャンクフードを食べた後、ホッとしたり、満足感を感じたりするのは、
脳内の報酬系を刺激して、
幸福感や快感を感じさせるセロトニンやドーパミンといった神経伝達物質が出るため
ということを、前回のブログで書きましたが、
脳内でセロトニンが分泌されるためには、
腸内細菌が、肉や魚などのタンパク質を材料にして作ってくれる「トリプトファン」というアミノ酸を、インスリンの働きで脳内へと運ぶことで合成されることがわかっています。
トリプトファンの脳への運搬役をしているインスリンというのは、
血糖値を下げるためのホルモンですが、どんな時に働くのでしょう?
そうです、
スイーツに含まれる「お砂糖」を摂って血糖値が上がったときなんです!
ということは、
ストレスを解消して、幸せを感じるセロトニンを作るために、
脳的には、甘いものやハンバーガー、揚げ物といったジャンクフードが手軽でもってこいということなんですね^^;
ですが、
こういった食べ物が問題なのは、私たちの体の機能を維持する上で不可欠なビタミンやミネラルといった栄養がほとんど含まれていないどころか、大量に含まれている添加物や化学物質、質の悪い油、砂糖や人工甘味料など、どれもが腸内で悪玉菌のエサとなってしまいます。
腸内フローラで優勢になった悪玉菌から発生する毒素が、
私たちの気分にも影響して、
過食へとつなげ
食習慣に影響するほど、
味覚も変えてしまう
という事がわかってきています。
このようなことから、
無性にジャンクフードや甘い物が食べたくなる、やめられない、止まらないとなった時は、
脳の報酬系が、腸内細菌によってコントロールされている状態ということが垣間見えてきて、
腸内細菌と脳が、ますます深く関係していると言えそうです。
ところで、セロトニンは脳で分泌されるというイメージが大きいかもしれませんが、
実は、脳に存在するのはたった2%だけで、残りの90%は腸にあり、食べたものから吸収した栄養を材料にして、腸内細菌によって作られているんです。
また、
快楽を感じさせる神経伝達物質のドーパミンの材料も、腸内細菌によって作られています。
感情に作用するセロトニンやドーパミンの大部分が腸で作られることからも、
私たちのメンタルに腸内細菌が大きく関わっていることがわかりますね^^
そして、
細菌やウィルスといった異物から私たちを守るために働いてくれる、免疫細胞の70%が、
腸に集中していることも忘れてはいけません^^
食べ物や花粉など、もともとは体には害のないものが、免疫のシステムによって異物=敵とみなされると、敵を追い出そうとする仕組みがはたらいて、くしゃみやかゆみなどといった、
さまざまな症状が起こるように、
体を守るための免疫が、逆に体を傷つけてしまう反応を「アレルギー」といいます。
アトピー性皮膚炎や、喘息、花粉症などのアレルギー性疾患の発症にも、
腸内環境が深くかかわっていることがわかってきています。
それでは、
心の状態や思考、アレルギー性疾患にまで影響する腸内は、
どういう状態が望ましいのでしょう?
安心してくださいね!
満足感や快感を感じるドーパミンやセロトニンの分泌は、
ジャンクフードに支配されっぱなしではないんです^^
ヘルシーな食べ物が好きな善玉菌が増えるような食べ物を食べて、
ジャンクな食べ物を好む悪玉菌をおとなしくさせると、
腸内細菌の構成は、
たったの24時間で変化が出始めると言われています。
そして善玉菌優勢に入れ替わった腸内細菌のバランスは、
私たちの健やかな気分と、健康的な食習慣へと導いてくれます^^
次回は、ストレスや環境で落ち込まないココロとカラダのために、
そして、アトピーや花粉症といったアレルギーへの影響とも切り離せない、
腸内環境を整える方法を一緒に学んでみましょう♪
みなさんの今日が、豊かで素敵な一日でありますように。
それではまた、次回のブログでお会いしましょう!
みらいこ代表のmidoriです。
今回は、
絶対に知っておくべき!ジャンクフードが無性に食べたくなる理由
ということで、強めのテーマですが、
私たちが普段、なんとなく、腸内環境やお肌に良くないとは感じつつ、
ついつい食べ続けてしまう魅惑のジャンクフードやファストフード、
レンチンだけで、調理せずに手軽に食べられる超加工食品、
チョコレートやケーキといったスイーツや菓子パン、
どうして美味しいと感じるのでしょうか?
どうして食べ続けてしまうのでしょうか?
その仕組みにとっても関係のある、
「食と心の状態」を、前回に引き続き、一緒に紐解いていきましょう^^
そして、
満足感や快感を感じると脳内に分泌する
ドーパミンやセロトニンを上手に働かせられるようになって、
「少しずつ」の良い選択に、
「勢い」がつき、
「いつの間にか習慣化」
こうなるとあなたの完全勝利です^^
食生活を健康的にコントロールできるようになると、
たまに寄り道しても、
そんな時は余裕で楽しんで♪
新しい習慣が、ちゃんと呼び戻して整えてくれますから安心してくださいね^^
さて、
「食と心の状態」をお話しする上で欠かせないのが、
私たちの「腸」の状態なんです
え!お腹の状態と、心の状態にどんな関係があるの??
と思いますよね^^
実は、
腸は、第二の脳と言われているくらい、私たちの感情に影響しているんです。
第二の脳?腸で何か考えるの??
と不思議になってきたでしょうか^^
脳と腸が連絡を取り合うために、間に入ってメッセンジャー的な役割をしてくれる
自律神経や、ホルモン、サイトカインといった伝達物質たちが働いてくれていて、
お互いに情報のやり取りをし、密接に影響を及ぼし合っているのですが、
研究によると、
脳が、 恐怖や苦痛、不安などの強いストレスを感じたとき、その情報が腸に伝わって、
消化吸収や、下痢や便秘といった腸の機能に影響が出る、
「脳→腸」
逆に、
腸で炎症が起きたり、腸内環境のいろいろな変化が脳に伝えられて、
脳での不安感が増し、行動や食欲に変化が起きる、
「腸→脳」
というように、
「脳⇄腸」相互に影響しあう作用があることが、わかってきています。
確かに、便秘が解消してお腹の調子が良くなると、
気分まで軽やかで、爽快になることがありますよね^^
こんなことから、
腸は「第二の脳」とも呼ばれていて、
「腸の状態が、あなたの心や嗜好に影響している」
ということにも納得がいくかもしれません^^
私たちの腸には、
腸内細菌という微生物が住んでいて、
なんと、一般的な成人の腸内細菌は約1000種類あり、
数にして100兆個、総重量にして1~2 kgと言われているように、
途方もない数の腸内細菌が、集団で生息しているんですね。
その様子を、お花畑や草むらに例えて「腸内フローラ」や「腸内細菌叢(そう)」と呼ばれているんです。
お花畑や、草むらと聞くと、
なんだか腸内一面に、ワ〜っと広がっている様子がイメージしやすいのではないでしょうか^^
腸内フローラは、
私たち一人一人、そのバランスが違っていて、
毎日の食べ物や飲み物、
薬などに含まれる抗生物質、
食品添加物中の化学物質や抗菌剤などの抗菌作用、
生活スタイル
によって、
あなたが生まれてから死ぬまでの間に、さまざまな変化が起こるんですね^^
そして、
私たちが、甘いものやジャンクフードを食べた後、ホッとしたり、満足感を感じたりするのは、
脳内の報酬系を刺激して、
幸福感や快感を感じさせるセロトニンやドーパミンといった神経伝達物質が出るため
ということを、前回のブログで書きましたが、
脳内でセロトニンが分泌されるためには、
腸内細菌が、肉や魚などのタンパク質を材料にして作ってくれる「トリプトファン」というアミノ酸を、インスリンの働きで脳内へと運ぶことで合成されることがわかっています。
トリプトファンの脳への運搬役をしているインスリンというのは、
血糖値を下げるためのホルモンですが、どんな時に働くのでしょう?
そうです、
スイーツに含まれる「お砂糖」を摂って血糖値が上がったときなんです!
ということは、
ストレスを解消して、幸せを感じるセロトニンを作るために、
脳的には、甘いものやハンバーガー、揚げ物といったジャンクフードが手軽でもってこいということなんですね^^;
ですが、
こういった食べ物が問題なのは、私たちの体の機能を維持する上で不可欠なビタミンやミネラルといった栄養がほとんど含まれていないどころか、大量に含まれている添加物や化学物質、質の悪い油、砂糖や人工甘味料など、どれもが腸内で悪玉菌のエサとなってしまいます。
腸内フローラで優勢になった悪玉菌から発生する毒素が、
私たちの気分にも影響して、
過食へとつなげ
食習慣に影響するほど、
味覚も変えてしまう
という事がわかってきています。
このようなことから、
無性にジャンクフードや甘い物が食べたくなる、やめられない、止まらないとなった時は、
脳の報酬系が、腸内細菌によってコントロールされている状態ということが垣間見えてきて、
腸内細菌と脳が、ますます深く関係していると言えそうです。
ところで、セロトニンは脳で分泌されるというイメージが大きいかもしれませんが、
実は、脳に存在するのはたった2%だけで、残りの90%は腸にあり、食べたものから吸収した栄養を材料にして、腸内細菌によって作られているんです。
また、
快楽を感じさせる神経伝達物質のドーパミンの材料も、腸内細菌によって作られています。
感情に作用するセロトニンやドーパミンの大部分が腸で作られることからも、
私たちのメンタルに腸内細菌が大きく関わっていることがわかりますね^^
そして、
細菌やウィルスといった異物から私たちを守るために働いてくれる、免疫細胞の70%が、
腸に集中していることも忘れてはいけません^^
食べ物や花粉など、もともとは体には害のないものが、免疫のシステムによって異物=敵とみなされると、敵を追い出そうとする仕組みがはたらいて、くしゃみやかゆみなどといった、
さまざまな症状が起こるように、
体を守るための免疫が、逆に体を傷つけてしまう反応を「アレルギー」といいます。
アトピー性皮膚炎や、喘息、花粉症などのアレルギー性疾患の発症にも、
腸内環境が深くかかわっていることがわかってきています。
それでは、
心の状態や思考、アレルギー性疾患にまで影響する腸内は、
どういう状態が望ましいのでしょう?
安心してくださいね!
満足感や快感を感じるドーパミンやセロトニンの分泌は、
ジャンクフードに支配されっぱなしではないんです^^
ヘルシーな食べ物が好きな善玉菌が増えるような食べ物を食べて、
ジャンクな食べ物を好む悪玉菌をおとなしくさせると、
腸内細菌の構成は、
たったの24時間で変化が出始めると言われています。
そして善玉菌優勢に入れ替わった腸内細菌のバランスは、
私たちの健やかな気分と、健康的な食習慣へと導いてくれます^^
次回は、ストレスや環境で落ち込まないココロとカラダのために、
そして、アトピーや花粉症といったアレルギーへの影響とも切り離せない、
腸内環境を整える方法を一緒に学んでみましょう♪
みなさんの今日が、豊かで素敵な一日でありますように。
それではまた、次回のブログでお会いしましょう!