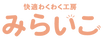脳と味覚を支配する腸内細菌!ー(腸脳相関)おさらい
みなさん、こんにちは^^
みらいこ代表のmidoriです。
前回のブログでは、脳と腸がお互いにコミュニケーションをとっていること(腸脳相関)、
そして、腸内細菌と心の状態の関係を通して、
ジャンクフードやスイーツが止められなくなる理由を紐解いてみました。
おさらいすると、
私たちの中で快感や満足感といった感情が生まれる仕組みは、脳内にあって、
人類が何百万年にわたって存続してきた過程で必要な、食欲や性欲といった本能的な快感を報酬として認識し、その報酬を求め続けるために脳内報酬系という神経回路があります。
そして、脳内報酬系と呼ばれている通り、
私たちの欲求が満たされたり、満たされそうだなと察知した時に、
「やったー!ご褒美だ!」と報酬がもらえるとばかりに活性化するんでしたね^^
この脳内報酬系を手っ取り早く活性化させ、満足感や解放感を得られるものとして、
砂糖や脂肪を多く含む高カロリーの食べ物は、脳内報酬系を強く刺激して、
快感や満足感を感じさせるドーパミンを分泌させます。
私たちの脳は、快感を覚えるものに執着するように進化してきたために、
更に甘いもの、脂っこいものへの欲求が強くなり、
やめられない、という依存状態を作るのでした。
また、
私たちの腸には、約1000種類もの腸内細菌が、
私たちが食べたものを餌にして生息していて、
消化吸収をおこなったり、
体内に侵入してきたウイルスや細菌を退治したり、
私たちの体調全体を整えてくれている、とってもありがたい存在なのですが、
体調管理だけではなく、食べたいもののチョイスまでも、
腸内細菌がコントロールしている可能性がわかってきているんでしたね^^
もう少し詳しく説明すると、
まるでお花畑のように、私たちの腸内に群生する腸内細菌は、腸内フローラ(花畑)と呼ばれ、
善玉菌、
悪玉菌、
日和見菌
それぞれの菌が、
最適なバランスを保つことによって、
私たちの身体の健康を維持してくれているのですが、
これらの腸内細菌同士、
手を取り合って仲良く共存しているかと思いきや、
実は、熾烈な生存競争をしていて、
自分がより成長できる栄養素を摂取するように宿主である私たちに働きかけたり、
逆に、ライバル種の腸内細菌が欲している栄養素を抑制するよう働きかけたり、
なかなかの駆け引きを繰り広げているとされています。
この駆け引きで、腸内細菌は、
宿主である私たちの味覚を感じる味覚受容体を変化させて、
特定の食品をより美味しく感じさせたり、
お腹が空いたという感覚をうながすホルモンを出したり、
食欲を抑えるように、迷走神経を介して脳に働きかけたりすることが分かっています。
さらに、
腸内細菌は、ライバル種の腸内細菌との生存競争に勝つために、
宿主の健康はかえりみず、自らの種の存続につながる働きをすることさえもある
という研究結果もあります。
腸内細菌によって、
私たちが不健康になるような嗜好や感覚に操られるって、ホラー映画のようですよね^^;
私たちがストレス解消の手段として、
お砂糖たっぷりのスイーツや、脂っこいジャンクフードを食べることによって、
満足感を得ることができる一方で、
大好物を与えられた悪玉菌の勢力が次第に拡大して、
「悪玉一派に支配されてしまう=ジャンクが止められない」
という負のスパイラルを引き起こしてしまうんですね^^;
ですが、裏を返せば、
善玉菌が好む栄養がとれる食事を心がけることで、
悪玉優勢から形勢が逆転し、ジャンクフードに対する渇望は薄れてくるということが言えます。
今日は腸内細菌と脳(心)の関係のおさらいが面白くなってきてしまい^^;
少し長くなってしまいましたので、
今日のブログのテーマに予定していた、腸内環境を整える方法「腸活」について、
近年よく話題になっていますね^^
改めてお話ししたいと思います。
みなさんの今日が、豊かで素敵な一日でありますように。
それではまた、次回のブログでお会いしましょう!
みらいこ代表のmidoriです。
前回のブログでは、脳と腸がお互いにコミュニケーションをとっていること(腸脳相関)、
そして、腸内細菌と心の状態の関係を通して、
ジャンクフードやスイーツが止められなくなる理由を紐解いてみました。
おさらいすると、
私たちの中で快感や満足感といった感情が生まれる仕組みは、脳内にあって、
人類が何百万年にわたって存続してきた過程で必要な、食欲や性欲といった本能的な快感を報酬として認識し、その報酬を求め続けるために脳内報酬系という神経回路があります。
そして、脳内報酬系と呼ばれている通り、
私たちの欲求が満たされたり、満たされそうだなと察知した時に、
「やったー!ご褒美だ!」と報酬がもらえるとばかりに活性化するんでしたね^^
この脳内報酬系を手っ取り早く活性化させ、満足感や解放感を得られるものとして、
砂糖や脂肪を多く含む高カロリーの食べ物は、脳内報酬系を強く刺激して、
快感や満足感を感じさせるドーパミンを分泌させます。
私たちの脳は、快感を覚えるものに執着するように進化してきたために、
更に甘いもの、脂っこいものへの欲求が強くなり、
やめられない、という依存状態を作るのでした。
また、
私たちの腸には、約1000種類もの腸内細菌が、
私たちが食べたものを餌にして生息していて、
消化吸収をおこなったり、
体内に侵入してきたウイルスや細菌を退治したり、
私たちの体調全体を整えてくれている、とってもありがたい存在なのですが、
体調管理だけではなく、食べたいもののチョイスまでも、
腸内細菌がコントロールしている可能性がわかってきているんでしたね^^
もう少し詳しく説明すると、
まるでお花畑のように、私たちの腸内に群生する腸内細菌は、腸内フローラ(花畑)と呼ばれ、
善玉菌、
悪玉菌、
日和見菌
それぞれの菌が、
最適なバランスを保つことによって、
私たちの身体の健康を維持してくれているのですが、
これらの腸内細菌同士、
手を取り合って仲良く共存しているかと思いきや、
実は、熾烈な生存競争をしていて、
自分がより成長できる栄養素を摂取するように宿主である私たちに働きかけたり、
逆に、ライバル種の腸内細菌が欲している栄養素を抑制するよう働きかけたり、
なかなかの駆け引きを繰り広げているとされています。
この駆け引きで、腸内細菌は、
宿主である私たちの味覚を感じる味覚受容体を変化させて、
特定の食品をより美味しく感じさせたり、
お腹が空いたという感覚をうながすホルモンを出したり、
食欲を抑えるように、迷走神経を介して脳に働きかけたりすることが分かっています。
さらに、
腸内細菌は、ライバル種の腸内細菌との生存競争に勝つために、
宿主の健康はかえりみず、自らの種の存続につながる働きをすることさえもある
という研究結果もあります。
腸内細菌によって、
私たちが不健康になるような嗜好や感覚に操られるって、ホラー映画のようですよね^^;
私たちがストレス解消の手段として、
お砂糖たっぷりのスイーツや、脂っこいジャンクフードを食べることによって、
満足感を得ることができる一方で、
大好物を与えられた悪玉菌の勢力が次第に拡大して、
「悪玉一派に支配されてしまう=ジャンクが止められない」
という負のスパイラルを引き起こしてしまうんですね^^;
ですが、裏を返せば、
善玉菌が好む栄養がとれる食事を心がけることで、
悪玉優勢から形勢が逆転し、ジャンクフードに対する渇望は薄れてくるということが言えます。
今日は腸内細菌と脳(心)の関係のおさらいが面白くなってきてしまい^^;
少し長くなってしまいましたので、
今日のブログのテーマに予定していた、腸内環境を整える方法「腸活」について、
近年よく話題になっていますね^^
改めてお話ししたいと思います。
みなさんの今日が、豊かで素敵な一日でありますように。
それではまた、次回のブログでお会いしましょう!